きょう:
*きょうの日付は合っていますか。日付の表示が合っていない場合は、こちらをご覧ください
*きょうの日付は合っていますか。日付の表示が合っていない場合は、こちらをご覧ください
- このプログラムは、明治6年(1873年)1月1日以降で有効です。
- これは、日本でのグレゴリオ暦の採用に係わるもので、一般に旧暦と呼ばれる天保暦(太陰太陽暦)の明治5年12月2日(グレゴリオ暦1872年12月31日)の翌日を、新暦と呼ばれる太陽暦の明治6年1月1日(グレゴリオ暦1873年1月1日)としました。そのため、和暦での明治5年12月3日から12月31日は存在せず、このプログラムではこのことに対応しておりません。
- 小の月や、閏年、改元に関わる日付などで、例えば「4月31日」と入力した場合、自動的に「5月1日」と読み替えて表示されます。
和暦 ⇒ 西暦 |
西暦 ⇒ 和暦 |
《改元日について》
明治45年〈1912年〉は7月30日、大正15年〈1926年〉は12月25日、昭和64年〈1989年〉は1月7日までです。ただし、大正・昭和の「改元の詔書」によれば、「明治45年7月30日」と「大正元年7月30日」、「大正15年12月25日」と「昭和元年12月25日」はともに存在します。これは即日改元であったためで、ちなみに昭和から平成へは翌日改元となり、昭和64年〈1989年〉は1月7日までで、平成元年〈1989年〉は翌日の1月8日からです。令和元年〈2019年〉は5月1日からです。
明治45年〈1912年〉は7月30日、大正15年〈1926年〉は12月25日、昭和64年〈1989年〉は1月7日までです。ただし、大正・昭和の「改元の詔書」によれば、「明治45年7月30日」と「大正元年7月30日」、「大正15年12月25日」と「昭和元年12月25日」はともに存在します。これは即日改元であったためで、ちなみに昭和から平成へは翌日改元となり、昭和64年〈1989年〉は1月7日までで、平成元年〈1989年〉は翌日の1月8日からです。令和元年〈2019年〉は5月1日からです。
[ 外部リンク ] 暦変換ツール【換暦】
|
|
|
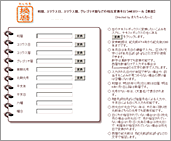 |
自分なりの法則を作っての、和暦と西暦の変換 |
||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
