[1] 春の七草とは(せり・なずな …)
= 春の七草・春の七種 =
|
春の七草
七草がゆの作り方
秋の七草
秋の七草の家紋
夏の七草
冬の七草
七草の英名
|
※ページ内の画像は、クリックして拡大することができます。
※ページ内の画像は、古文書からの引用を除いて全て当サイトのオリジナルです。転用・転載を禁じます。
|
[1] 春の七草とはなんでしょうか?
春の七草を声に出して読んでみましょう。
- 新しい年を祝いお正月気分がまだちょっと残っている1月7日は、五節句の一つ「
人日の節句
」です。この日には「七草粥」を食べて邪気を祓い、一年の無病息災と五穀豊穣を祈るとされる風習があります。[五節句とは ▶]
- この日は、「七草」「七草の節句」「七草の祝い」などとも言われます。
注:「七草」は、七種類の意味の「七種」とも書かれる。
注:「節句」は、本来の用字は「節供」とする説がある。
- では、「七草」とは何を指すのでしょうか。「七草」の起源は何でしょうか。ここでは、それらを見てみたいと思います。
- 七草の種類は、次のような「五七五七七」の覚えやすい短歌調で現代に伝わります。
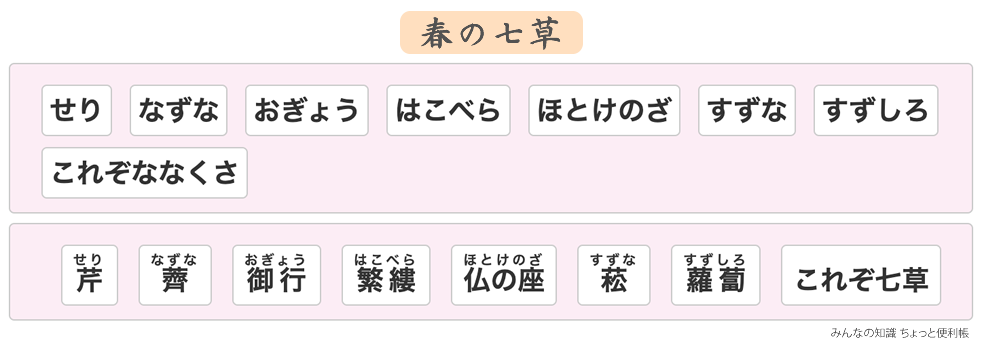
せり
なずな
おぎょう
はこべら
ほとけのざ
すずな
すずしろ
これぞななくさ
芹
薺
御行
繁縷
仏の座
菘
蘿蔔
これぞ七草
注:「 おぎょう」は「 ごぎょう」とも呼ばれますが、ここでの読み方は、 『ごぎょうは誤り』とする植物学者・牧野富太郎博士の説 に拠りました。近年、一般には「 ごぎょう」とするものが多く見られるようですが、植物を扱った専門書などでの「七草」の解説では「 おぎょう」とするものが見られます。
- では、「せり・なずな・おぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」の、現在言われている種類などを見てみます。
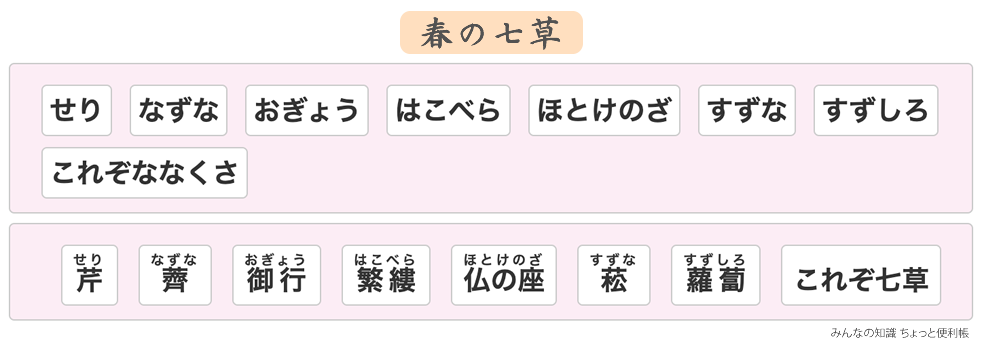
※写真は拡大することができます。
名称など |
備考 |
|
セリ
芹
セリ科
|
セリの若菜は香りが良く、お浸しなどの食用に。「七草」の時期以外でも鍋物などに使われる。
|
|
ナズナ
薺
アブラナ科
|
ナズナの別名はペンペングサ、シャミセングサ、バチグサなど。 かつては冬の貴重な野菜で、若苗を食用にする。
江戸時代の民間での七草粥の材料は、江戸ではナズナに小松菜を加え、関西ではナズナにカブを加えた二種ほどであった。〔後述〕
|
|
オギョウ
(ゴギョウ)
御行
御形
キク科
|
オギョウは、ハハコグサ(母子草)のこと。
オギョウは、ゴギョウとも。一般には「ゴギョウ」とするものが多く見られる。
ハハコグサは、ホウコグサとも。生薬名で
鼠麹草。
この植物の名称について、植物学者の 牧野富太郎(1862-1957)は、1919年〈大正8年〉の入江弥太郎との共著 「雑草の研究と其利用」で、『ははこぐさ(鼠麹草) (略)一名 ごぎうと称す。是れ宜しく おぎゃう(御行と書す)ならざるべからず』とし、「 おぎょうでなくてはならない」としている。
また、「オギョウは御行と書くがこれをゴギョウと言うのは
可
くない」( 『植物記(1943年・昭和18年)』)、『ゴギョウは誤』( 『図説普通植物検索表(1950年・昭和25年)』)としている。また、「五行、五形と書くのは非」(『植物記』『植物一日一題』)としている。
|
|
ハコベラ
繁縷
蘩蔞
ナデシコ科
|
ハコベのこと。古名でハクベラとも。
お浸しなどの食用にできるほか、小鳥に野菜代わりの餌として食べさせたりする。
ハクベラは「波久倍良」として、平安時代の辞書類の『新撰字鏡』や、『本草和名』、『和名類聚抄』などに見られる他、『拾芥抄』に「蘩蔞」のルビとして見られる。
|
|
ホトケノザ
仏の座
タビラコは
キク科
現在の
ホトケノザは
シソ科
|
現在の紫紅色の花を付けるホトケノザではなく、タビラコ(田平子)を指し、食用にするのはコオニタビラコ(小鬼田平子)とされる。
ただし、オオバコの絵を描く文献〔古今沿革考・後述〕や、七種類の中にホトケノザとタビラコの双方をあげる文献〔壒嚢鈔・後述〕もあったりする。
現在の紫紅色の花を付けるホトケノザはシソ科だが、食には絶えられない。春の七草のタビラコはキク科で黄色い花を付ける。タビラコは、カワラケナとも。
|
|
スズナ
菘
菁
鈴菜
アブラナ科
|
カブ(蕪)のこと。
|
|
スズシロ
蘿蔔
清白
アブラナ科
|
ダイコン(大根)のこと。
|
【リンク】牧野富太郎ほか著による『児童野外植物のしをり』に書かれた「春の七草」と挿絵
1912年・明治45年(国会図書館デジタルコレクション)
- これまで述べたように、現在の「七草」はこのような植物として一般化しています。
せり
なずな
おぎょう
はこべら
ほとけのざ
すずな
すずしろ
これぞななくさ
芹
薺
御行
繁縷
仏の座
菘
蘿蔔
これぞ七草
- では、次から、七草の起源などについて見てみたいと思います。
- が、ちょっとその前に……
|
- このサイトでは、いくつかの文献を引いていますが、この他にも文献や説があることも考えられ、ここに述べたことが全ての情報ではありません。皆様からのご指摘をお待ち致します。
- このページは、例のいくつかをあげ編集しています。
- 学習や研究などにお使いの際は、辞典・専門書などでご確認ください。(このページを利用され、何らかの不利益や問題が生じても、当サイトは一切の責を負いかねます。あらかじめご了承ください)
- 本サイトは編集著作物です。データの無断転載等を禁じます。
 著作権侵害という犯罪 著作権侵害という犯罪
|
Last updated : 2025/10/18










